![]() ボランティア関連ニュース(外部記事)
ボランティア関連ニュース(外部記事)
- 医療・福祉・人権
- 災害救援・地域安全活動
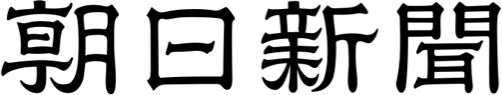
多様な人材確保へ、保護司法改正案が閣議決定 任期を2年から3年に
2025.11.10
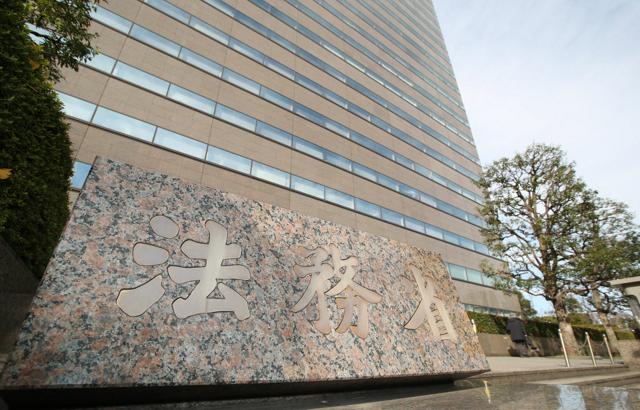
刑務所から仮釈放された人や、保護観察中の少年らの立ち直りを支える「保護司」の担い手を増やそうと、政府は11日、保護司法の改正案を閣議決定した。「多様な人材」の確保を明記し、任期を今の2年から3年に延長する。臨時国会での成立をめざす。
さらに、滋賀県大津市で昨年5月、自宅で面接中だったとみられる保護司が殺害された事件を受け、保護司が安全に面接に臨める場所の確保や支援体制の整備を、国の責務とした。
保護司は、無報酬のボランティアだが、法相の委嘱を受ける非常勤の国家公務員。刑事司法手続きのアンカーとして再犯を防ぐ「更生保護」の一翼を担う。
明治期の篤志家の活動がルーツとされる日本独自の制度で、国際的な評価も高いが、高齢化となり手不足に直面している。
法務省の「犯罪白書」などによると、2000年には約4万9千人いたが、今年は約4万6千人に。一方で平均年齢は63.3歳から65.4歳へと上昇した。年齢別の構成でみると、60歳以上が8割を占める。
法務省の担当者は「これまでは地域の名士から名士へと受け継がれる傾向にあったが、地域社会のつながりが薄れ、新しい担い手を見つけにくくなっている」と話す。
こうした状況を受け、改正案では、保護司の要件から「社会的信望」や「時間的余裕」があることを削除し、「人格識見が高い」「必要な時間を確保できる」と改めた。いまの文言ではハードルが高いと受け止められる恐れがあるためだ。
保護司の使命として掲げていた「社会の浄化」という表現も、時代にあわないとして見直し、「安全な地域社会の実現」を図るとした。
そのうえで、保護司を推薦する保護観察所長は、地域の民間団体や個人の協力を得て「多様な人材」の確保に努めると明記。現役世代の人が保護司を務めやすいよう、民間企業が休暇の取得などに配慮することを努力義務にした。
保護司の活動のため休暇をとったことなどを理由に、解雇など不利益な扱いをすることを禁じる規定も盛り込んだ。
■報酬制の導入は見送り
今回の改正は、有識者による検討会が昨年10月にまとめた報告書を受けたものだ。検討会では報酬制の導入も検討されたが、「無報酬だからこそ罪を犯した対象者が心を許してくれる」などと慎重な意見が多く見送られた。
法務省はすでに、新任のときの年齢は「66歳以下」としていた制限をなくし、自宅以外の面接場所を増やすなど、法律以外の見直しを進めている。(二階堂友紀)
さらに、滋賀県大津市で昨年5月、自宅で面接中だったとみられる保護司が殺害された事件を受け、保護司が安全に面接に臨める場所の確保や支援体制の整備を、国の責務とした。
保護司は、無報酬のボランティアだが、法相の委嘱を受ける非常勤の国家公務員。刑事司法手続きのアンカーとして再犯を防ぐ「更生保護」の一翼を担う。
明治期の篤志家の活動がルーツとされる日本独自の制度で、国際的な評価も高いが、高齢化となり手不足に直面している。
法務省の「犯罪白書」などによると、2000年には約4万9千人いたが、今年は約4万6千人に。一方で平均年齢は63.3歳から65.4歳へと上昇した。年齢別の構成でみると、60歳以上が8割を占める。
法務省の担当者は「これまでは地域の名士から名士へと受け継がれる傾向にあったが、地域社会のつながりが薄れ、新しい担い手を見つけにくくなっている」と話す。
こうした状況を受け、改正案では、保護司の要件から「社会的信望」や「時間的余裕」があることを削除し、「人格識見が高い」「必要な時間を確保できる」と改めた。いまの文言ではハードルが高いと受け止められる恐れがあるためだ。
保護司の使命として掲げていた「社会の浄化」という表現も、時代にあわないとして見直し、「安全な地域社会の実現」を図るとした。
そのうえで、保護司を推薦する保護観察所長は、地域の民間団体や個人の協力を得て「多様な人材」の確保に努めると明記。現役世代の人が保護司を務めやすいよう、民間企業が休暇の取得などに配慮することを努力義務にした。
保護司の活動のため休暇をとったことなどを理由に、解雇など不利益な扱いをすることを禁じる規定も盛り込んだ。
■報酬制の導入は見送り
今回の改正は、有識者による検討会が昨年10月にまとめた報告書を受けたものだ。検討会では報酬制の導入も検討されたが、「無報酬だからこそ罪を犯した対象者が心を許してくれる」などと慎重な意見が多く見送られた。
法務省はすでに、新任のときの年齢は「66歳以下」としていた制限をなくし、自宅以外の面接場所を増やすなど、法律以外の見直しを進めている。(二階堂友紀)
