![]() ボランティア関連ニュース(外部記事)
ボランティア関連ニュース(外部記事)
- 医療・福祉・人権
- 子ども・教育
- 多文化共生・国際協力
- スポーツ
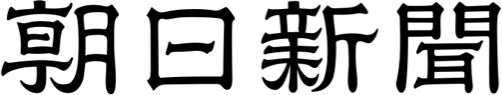
筑波技術大、デフリンピックで世界と交流 選手やボランティア派遣
2025.11.11

聴覚障害のあるデフアスリートが競う「デフリンピック」。15日から日本で初開催される国際スポーツ大会に、聴覚と視覚の障害者を対象に開学した国内唯一の高等教育機関、筑波技術大(茨城県つくば市)が選手やボランティアらを送り出す。大学は学生の異文化交流にも期待する。
「『聞こえる』『聞こえない』の壁を取っ払い、一生懸命取り組めば、この先の人生にいきる」。今月、つくば市の天久保キャンパスであった選手らの壮行会。サッカー女子日本代表の中心選手で、前回のブラジル大会に続いて出場する同大学の卒業生、岩渕亜依選手が手話を交えながら後輩たちに呼びかけた。
今回は、東京都内を中心に26日まで、世界各国・地域の代表約3千人が21競技に臨む。同大学からは学生が6人、卒業生11人が選手として出場。さらには開閉会式のパフォーマーとして2人、サポートスタッフ(ボランティア)として108人が参加する。いずれも耳が聞こえなかったり聞こえにくかったりする学生が学ぶ産業技術学部の学部生や大学院生だ。
ボランティア学生は大会中、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターを拠点に、習得した「国際手話」を通して海外の選手やスタッフらのサポートなどをする。
デフリンピックは1924年のパリ大会から数えて100周年を迎えた。大学はこの節目を「貴重な機会」ととらえ、観客としても参加できるように、産業技術学部は約2週間分の講義を前倒しで終わらせ、大会中は休講にする。
デフリンピックと大学の関わりは深い。たとえば、初出場となるハンドボール男子代表チームは、3年前に発足した学内サークルが前身だ。卒業生の小林優太主将は「練習は2人のキャッチボールで終わるのが日常だった。まずは1勝して未来への一歩を踏み出せたら」と意気込む。
手話の手と花の形をあしらった大会エンブレムは、卒業生の多田伊吹さんが在学中に手がけたものだ。
冒頭の壮行会で、産業技術学部3年の文倉周音さんはボランティアを代表して「笑顔で精いっぱいサポートしたい」と語った。石原保志学長は「選手として、パフォーマーとして、ボランティアとして参加するみなさんを応援する。世界中の人と交流してほしい」と期待を込めた。(床並浩一)
◇
〈筑波技術大学〉 短大から移行して2005年に開学し、聴覚と視覚の障害者に特化した教育がなされている。「産業技術学部」「保健科学部」のほか、25年には「共生社会創成学部」が開設。学生数は約300人。健康づくりや障害者スポーツの振興を担う人材を養成するため、26年4月には保健科学部保健学科に「健康スポーツ学コース」が新設される。キャンパスは茨城県つくば市の天久保と春日の両地区にある。(床並浩一)
「『聞こえる』『聞こえない』の壁を取っ払い、一生懸命取り組めば、この先の人生にいきる」。今月、つくば市の天久保キャンパスであった選手らの壮行会。サッカー女子日本代表の中心選手で、前回のブラジル大会に続いて出場する同大学の卒業生、岩渕亜依選手が手話を交えながら後輩たちに呼びかけた。
今回は、東京都内を中心に26日まで、世界各国・地域の代表約3千人が21競技に臨む。同大学からは学生が6人、卒業生11人が選手として出場。さらには開閉会式のパフォーマーとして2人、サポートスタッフ(ボランティア)として108人が参加する。いずれも耳が聞こえなかったり聞こえにくかったりする学生が学ぶ産業技術学部の学部生や大学院生だ。
ボランティア学生は大会中、東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターを拠点に、習得した「国際手話」を通して海外の選手やスタッフらのサポートなどをする。
デフリンピックは1924年のパリ大会から数えて100周年を迎えた。大学はこの節目を「貴重な機会」ととらえ、観客としても参加できるように、産業技術学部は約2週間分の講義を前倒しで終わらせ、大会中は休講にする。
デフリンピックと大学の関わりは深い。たとえば、初出場となるハンドボール男子代表チームは、3年前に発足した学内サークルが前身だ。卒業生の小林優太主将は「練習は2人のキャッチボールで終わるのが日常だった。まずは1勝して未来への一歩を踏み出せたら」と意気込む。
手話の手と花の形をあしらった大会エンブレムは、卒業生の多田伊吹さんが在学中に手がけたものだ。
冒頭の壮行会で、産業技術学部3年の文倉周音さんはボランティアを代表して「笑顔で精いっぱいサポートしたい」と語った。石原保志学長は「選手として、パフォーマーとして、ボランティアとして参加するみなさんを応援する。世界中の人と交流してほしい」と期待を込めた。(床並浩一)
◇
〈筑波技術大学〉 短大から移行して2005年に開学し、聴覚と視覚の障害者に特化した教育がなされている。「産業技術学部」「保健科学部」のほか、25年には「共生社会創成学部」が開設。学生数は約300人。健康づくりや障害者スポーツの振興を担う人材を養成するため、26年4月には保健科学部保健学科に「健康スポーツ学コース」が新設される。キャンパスは茨城県つくば市の天久保と春日の両地区にある。(床並浩一)
